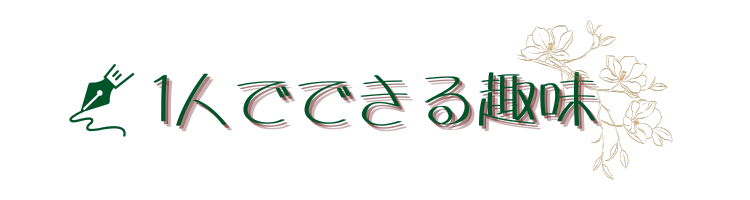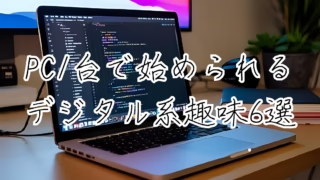- 楽器が弾けなくても、スマホアプリやAIツールを使って、知識ゼロから気軽に作詞作曲を始める方法。
- 0円から始める方法から本格的な機材まで、予算別の道具の揃え方を知ることができます。
- 初心者でもオリジナル曲を完成させられる、テーマ決めからアレンジまでの具体的な7ステップを解説します。
- 完成した曲をSNSで発表する方法や、同じ趣味の仲間を見つけるヒントも知ることができます。
『自分だけの歌』今日から作ってみませんか?
「自分だけの曲を作ってみたい」。 ふとした瞬間に、そんな風に思ったことはありませんか?
作詞作曲は、特別な才能や専門知識がなくても始められる、クリエイティブな趣味です。
作詞作曲で毎日がもっと輝きだす3つの理由

脳の活性化につながる
作詞作曲は、感性を司る右脳と、論理を司る左脳を同時にフル活用する、非常にクリエイティブな活動です。
どんな言葉を選べば想いが伝わるか(作詞)、どんな音の並びが心地よいか(作曲)、そして曲全体をどう組み立てるか(構成)。
この一連の創造的なプロセスは、脳の様々な領域を結びつけ、認知機能や問題解決能力に良い刺激を与えると考えられています。
一生モノのスキルと作品が手に入る
一度身につけた作詞作曲のスキルは、簡単に失われるものではなく、あなたの人生を豊かに彩る「一生モノの財産」になります。
あなたが制作した楽曲は、デジタルデータや楽譜として半永久的に残り、その時々の感情や思い出が詰まったものになります。
数年後に聴き返したとき、当時の情景が鮮やかに蘇るかもしれません。
それは、写真や日記とはまた違った形で、あなたの人生を記録してくれる、かけがえのない宝物になるでしょう。
新しい世界とつながるきっかけに
自分で作った曲を、誰かに聴いてもらいたい。そんな気持ちが芽生えたら、あなたの世界はさらに大きく広がります。
今や、SNSや動画サイトを使えば、誰でも簡単に自分の作品を世界中に発信できる時代です。
同じ趣味を持つ仲間と出会い、感想を伝え合ったり、一緒に音楽を創ったり。
作詞作曲という共通言語が、新しい出会いやコミュニティへとあなたを導いてくれるでしょう。
知識ゼロでも大丈夫!最初の「一歩」を踏み出す方法

ゲーム感覚で音楽アプリに触れてみる
「楽器が弾けないから作曲なんて…」と思っている方にこそ、試してほしいのが音楽制作アプリやAIツールの活用です。
今は、専門知識がなくても、まるでゲームのように音楽を創り出せる時代になりました。
スマートフォンやパソコンで使える音楽制作アプリです。
例えば「GarageBand(ガレージバンド)」などが有名で、楽譜が読めなくても、ブロックを組み合わせるような感覚で直感的に音を並べ、リズムや伴奏を組み立てることができます。
「こんな音を重ねると、こんな雰囲気になるんだ」という発見を楽しみましょう。
さらに手軽な方法がAI作曲アプリの活用です。
作りたい曲のイメージや歌詞を文字で入力するだけで、AIが自動でメロディー、伴奏、さらには歌声まで乗せた本格的な楽曲を生成してくれます。
「歌詞が思いつかない…」という場合は、ChatGPTのような生成AIに相談してみるのも一つの手です。
「夕暮れの海辺をテーマにした、切ない歌詞のアイデアをください」のように話しかけるだけで、作詞の手伝いをしてくれます。
このように、アプリやAIを賢く使うことで、「作曲」や「作詞」のハードルは劇的に下がります。
まずは遊び感覚で、これらのツールに触れてみることから始めてみましょう。
あなたの創作スタイルは?予算別・作曲道具の揃え方
「作曲を始めるには、高価な機材がたくさん必要なのでは?」と心配されるかもしれません。
確かに、本格的に仕事として行うにはかなり高額な機材が必要ですが、趣味として始めるなら、様々な選択肢があります。
ここでは、3つのコースに分けて、具体的な道具の揃え方をご紹介します。
【0円コース】まずはスマホ一台でOK
今はあなたがお持ちのスマートフォンだけで、曲作りは始められます。
まずは「曲作りの雰囲気を体験してみたい」という方には、この0円コースがおすすめ。
【3万円コース】パソコンで本格的に挑戦
「スマホだけじゃ物足りない」「もっと高音質で録音したい」と感じ始めたら、パソコンを中心とした制作環境にステップアップしてみましょう。
ご自宅にパソコンがあれば、約3万円の追加投資で、プロも使う環境の第一歩が手に入ります。
このセットがあれば、自分の歌や演奏を、より本格的な作品として形にすることができます。
【10万円〜コース】高音質での録音や演奏も
さらに創作の幅を広げたい、クオリティを追求したいという方は、機材を少しずつグレードアップしていきましょう。
もちろん、最初から全てを揃える必要はありません。
自分の創作スタイルに合わせて、必要なものを一つずつ買い足していくのも、趣味の醍醐味の一つです。
知識ゼロからオリジナル曲を完成させる7つのステップ例
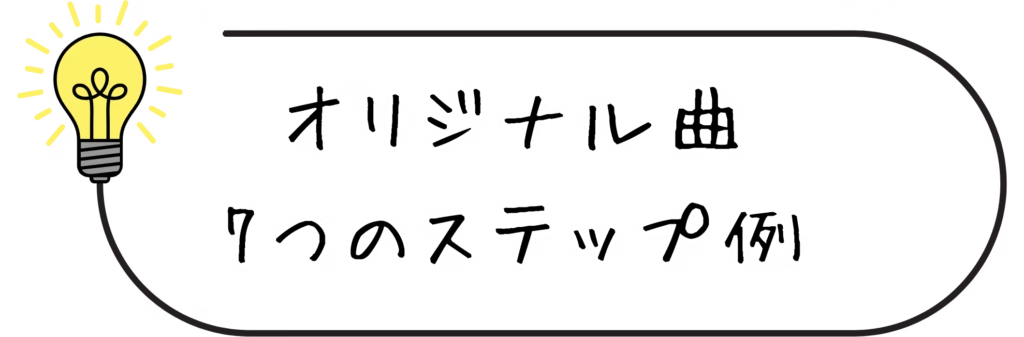
ここからは、実際にオリジナル曲を完成させるまでの具体的な手順の例を、7つのステップに分けて紹介していきます。
以下のやり方は「詞先(しせん)」と呼ばれる手法です。
「曲先(きょくせん)」と呼ばれる作曲を先にする手法より難しいと言われています。
自分に合う方で取り組んでみてください。
Step 1: 曲の「テーマ」を決める
どんな曲にも、中心となる「テーマ」があります。
「嬉しい」「悲しい」といった感情でもいいですし、「帰り道の夕焼け」「大切な人への感謝」といった情景やメッセージでも構いません。
まずは、あなたが今、歌にしてみたいことは何か、心に問いかけてみましょう。
難しく考えず、一つだけキーワードを決めるだけでも大丈夫です。
Step 2: 物語を紡ぐ「作詞」に挑戦
テーマが決まったら、次は作詞に挑戦してみましょう。
多くのJ-POPで使われる基本的な構成は「Aメロ(物語の説明)→Bメロ(サビへの盛り上げ)→サビ(一番伝えたいこと)」という流れです。
まずは、曲の中で一番伝えたいメッセージ=「サビ」の歌詞から考えてみると、全体の物語が作りやすくなります。
もし、「言葉が何も思い浮かばない…」と手が止まってしまったら、生成AIの力を借りるのも一つの現代的な方法です。
例えばChatGPTなどに「『夏の終わりの切なさ』をテーマにした歌詞のアイデアをください」とお願いすれば、インスピレーションのきっかけとなる言葉やフレーズをたくさん提案してくれます。
Step 3: 心に響く「コード進行」を選ぶ
歌詞の世界観が見えてきたら、曲の土台となる「コード進行」を選びます。
「コード」とは、複数の音を同時に鳴らした「和音」のこと。
これが連なることで、曲の雰囲気(明るい、切ないなど)が決まります。
聴いていて心地よいと感じる「定番のコード進行」というものが存在します。
例えば「C→G→Am→F」という進行は、数えきれないほどのヒット曲で使われています。
音楽制作アプリには、こうした定番のコード進行を自動で演奏してくれる機能があったり、「コード進行 おすすめ」などで検索すれば、たくさんのパターンが見つかります。
まずは好きな響きのものを一つ選んでみましょう。
Step 4: 「メロディー」を口ずさんでみる
選んだコード進行をループ再生させながらBGMにして、いよいよメロディー作りです。
再生されるコードに合わせて、自由に「ラララ」や「フフフ」で歌ってみるだけです。
そして、その鼻歌をスマホのボイスメモにどんどん録音していきましょう。
ここでは上手く歌おうとせず、思いつくままに色々なメロディーを試すのがコツです。
録音したものを後で聴き返し、「このフレーズ、いいな」と感じたものを繋ぎ合わせていくと、Aメロ、Bメロ、サビのメロディーが形になっていきます。
Step 5: 曲の「構成」を組み立てる
Aメロ、Bメロ、サビというパーツが出揃ったら、それらを並べて一曲の「構成」を組み立てます。
イントロ → 1番(Aメロ → Bメロ → サビ)→ 間奏 → 2番(Aメロ → Bメロ → サビ)→ Cメロ(展開)→ 最後のサビ → アウトロ
もちろん、この通りでなくても構いません。
Cメロをなくしたり、サビを繰り返したり、自由に組み替えて、最もドラマチックに伝わる流れを探してみましょう。
Step 6: 楽器で彩る「アレンジ」の初歩
メロディーとコードだけの状態は、言わば「弾き語り」の状態。
ここに様々な楽器の音を加えて、曲を華やかに彩っていくのが「アレンジ(編曲)」です。
音楽制作アプリを使えば、まるでブロックを置くように、ドラムやベース、ピアノの音を簡単に追加できます。
- ドラム
- まずはシンプルなリズムパターンを選んで、曲全体に入れてみましょう。
- ベース
- コードのルート音(Cのコードなら「ド」の音)を追いかけるだけで、曲に安定感が生まれます。
- ピアノやストリングス
- コードを奏でるだけでも、曲に厚みと彩りが加わります。
- 最初は音を足しすぎず、主役であるメロディー(歌)を引き立てることを意識するのがポイントです。
Step 7: とにかく「完成」させてみる
これが最も大切なステップです。
作っている途中で「なんだかイマイチだな…」と感じる瞬間は、誰にでも必ず訪れます。
しかし、そこで手を止めてはいけません。
たとえ100点満点だと感じられなくても、とにかく最後まで作りきり、「完成」という経験をすることが、次の一曲への大きなステップになります。
完成した曲を世界に届けよう!発表の場と仲間探し
「誰かに聴かせるなんて、恥ずかしい…」と感じるかもしれませんが、勇気を出して発表してみることで、作詞作曲はもっともっと楽しくなります。
なぜ発表することが大切なのか
自分の作品を公開し、誰かから「いいね」や感想をもらえると、次の一曲へのモチベーションが驚くほど湧いてきます。
また、客観的な意見をもらうことで、自分では気づかなかった長所や改善点が見つかり、スキルアップにも繋がります。
気軽に始められる発表の場
今は、誰もがクリエイターになれる時代。
無料で、かつ匿名で作品を発表できる場所がたくさんあります。
仲間を見つけてもっと楽しく
一人で黙々と続けるのも素敵ですが、同じ趣味を持つ仲間がいると、楽しさは何倍にも膨らみます。SNSなどで気になるクリエイターを見つけたら、勇気を出してコメントを送ってみましょう。
「この曲の、こういうところが好きです」と具体的に伝えるのがおすすめです。
お互いの曲を聴き合ったり、情報交換をしたりすることで、一人では得られない知識やインスピレーションが手に入り、創作活動がより豊かなものになるはずです。
あなただけのメロディーが、誰かの心を動かす日
今日、あなたが何気なく口ずさんだ鼻歌が、明日には美しいメロディーになり、誰かの心をそっと温める歌になるかもしれません。
あなたが書き留めた一行の言葉が、未来の誰かを勇気づける歌詞になるかもしれません。
もし少しでも興味が出てきたら、お持ちのスマートフォンから気軽に始めてみましょう。
あなただけのメロディーが生まれる瞬間を、心から応援しています。